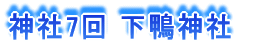今回:神社7回 下鴨神社
前回:寺57回
三十三間堂
(次回の更新予定:6月1日)
|
近況(2023年5月1日 記)
3月は気温が高く、全国的に桜の咲くのが早かった。
須磨アルプスの山桜も早くから満開になり、
つられて鴬(ウグイス)も早くから啼きだしていた。
例年、当初はへたな啼き方なのだが、
今年は最初から上手(じょうず)に啼くやつがいた。
4月に入って春本番である。
新緑が美しい。
鶯たちは、あちこちで盛んに啼く。
彼らもこの春の陽気と新緑を楽しんでいるのであろう。
鶯の啼き声を聞きながら、
新緑の山道を歩くのは何とも楽しい。
ところが、声はすれども姿は見えずで、鶯の姿は滅多に見かけない。
見えても瞬間的である。
過日、山の仲間のSt氏が、
その鶯を見事に写真に収めて送ってきてくれた。
鶯とメジロの姿は似ているが、
残念ながら、その美しさはメジロに負ける。

4月2日(日曜日)に
山の仲間の「屋外懇親会(野外懇親会)」があった。
桜の満開の頃に開催することは早くから決まっていて、
4月2日のころなら満開であろうと思われた。
ところが、今年は3月中に満開になってしまったのである。
しかし、当日はなんとか桜は散らずに我々を迎えてくれた。
Fn氏が「屋外懇親会」開催のチラシを事前に配られて、
当日15名ほど集まった。
例によって飲み物(アルコール類)と弁当を、
各自持参の集まりである。
下の写真には、前列に子供達が写っているが、
これはImさんが、
お孫さんと近所の子を引き連れて見学に来たのである。

野外懇親会と言っても、メインはカラオケである。
12時に集まって、3時ごろまで盛んに歌った。
私は、湯沸かしの道具を持参して、
720mlの清酒を燗にして飲んだ。
すっかり酔っぱらって帰路は、
自宅までSt氏に同道願った次第であった。

4月4日(火)にKS会があった。
この会も早くから決まっていた。
2日前に山の仲間の「野外懇親会」があったばかりだが、
春の陽気に誘われて開催されるのは仕方がない。
当初の計画では、
12時半に例の梅田のホテル6階の「桂」に集合し、会席料理をいただいて、
3時から1階の喫茶店でお喋りして解散となっていた。
私は面倒を見て頂いているIg氏に、
この季節だから「堂島川」を散策しようと提案しておいた。
淀川の支流、堂島川に沿った散策路には桜並木があって、
ちょうど満開である。


「堂島川散策」が終わって解散だが、
急きょ「カラオケ」に行こうとなった。
女性は帰るというが、男性3人は行くことになった。
しかし例のスナック「if」の開店は5時からである。
Ig氏はスナックのママに電話して、
4時に開けてくれるように交渉した。
さすがにIg氏は、長年の常連である。
ママは了解したらしい。
われわれ男子3人は、スナックに向かう。
まだ明るいスナックは貸し切りで、
ママを含めた4人の集まりである。
大いに歌い、飲んだ。
ブランデーのような強い酒を飲んだものだから、
私はすっかり酔っぱらった。
「if」にどれほどの時間居たであろうか。
外に出た時は既に日は落ちていた。
私はNz氏と腕を組んでやっとの思いで大阪駅に辿り着く。
その後の記憶は定かではないが、
帰宅は午後の8時を過ぎていた。

4月10日、京都に出掛けた。
訪ねたのは、曼殊院(まんしゅいん)、下鴨神社、上賀茂神社である。
京都の神社仏閣への訪問も、これが最後になる予定だ。
2019年にこのホームページのタイトルを
「山と温泉」から「寺・神社・城」に換えて4年になる。
計画では(私も歳だから)、遠くに車で出かけるのは敬遠して、
訪ねたのは奈良、京都を中心とした近辺ばかりである。
現在まで右の目次のように、
寺57、神社17、城10ヶ所、合計84ヶ所訪れている。
ここに来て、奈良・京都の寺・神社を訪ね尽くしてしまったのだ。
「訪ね尽くしてしまった」というのは言い過ぎで、
寺・神社は、まだまだ沢山あるのだが、
有名な寺・神社を基本としているので、
こんな言い方になった次第である。
有名な寺・神社・城には、歴史的なエピソードが多く、
関係する著書も多い。
さて、これからである。
私も歳だから、もうこの辺で、
このホームページも終了にしてもよいのだが
20年以上続けてきたのである。
終わってしまうには未練がある。
あと3年、85歳まで続けられないだろうか
(生きていれば、の話だが)。
とすると、車で(あるいは電車で)遠くに出掛けることになる。
月に一度掲載するとして、3年では36ヶ所だ。
頑張ってみることにする。

先月の本欄にメダカの孵化について書いた。
生まれたのである。
産卵床を入れて翌日には既に産卵していた。
私は驚き、感激した。
こんなに容易に産卵するものか。
上の写真は5日後のものだが、産卵床に沢山の卵が付いている。
メダカのメスは、オスがいなければ産卵しないらしい。
自然の不思議である。
調べると夜に産卵するという。
だから、朝起きて観察してみると、卵の数がふえているのだ。
卵の大きさは約1㎜ほどである。
この卵の大きさはヒトの受精卵(0.14㎜)に比べて極めて大きい。
これは発生までの栄養分を卵の中に保持していなければならず、
哺乳動物のように母親から供給されないからである。
産卵から孵化までの日数は、水温25℃で約10日らしい。
孵化して稚魚が生まれると危ない事がある。
親が子を食うというのだ。
それで、卵の付いた産卵床を別の水槽に移す必要があった。

10日間で孵化するというのだが、なかなか生まれてこない。
2週間目に水槽をのぞくと稚魚、
2匹が泳いでいるのを見た時には感激した。
あの小さな1㎜ほどの卵から生まれてきたのである。
上の写真で、一番小さく見えるのが生まれたてである。
3㎜ほどであろうか。
それにしても、小さな卵から、
直ぐに泳ぎ出す生命が誕生するのが不思議だ。
生まれて直ぐに泳ぎ回る。
考えてみれば、人間様の赤子は何も出来ないのだ。
さて、針子の餌である。
なにせ、
この小さなメダカの稚魚(針子という)が食べられる餌である。
普通のメダカの餌ではない。
アマゾンに「針子の餌」を注文すると、
翌日、粉のような餌が届いた。
現在、稚魚の成長を、興味を持って観察している。

歳を取ると風呂に入るのも面倒である。
以前は、
夕食が終わって寝る前に入浴という事になっていたのだが、
この頃は(酒が入っているからか)風呂に入る元気がない。
だから、元気な昼間に入ることにしている。
先日、4時ごろに入浴し、
裸でうろうろしていたら電話が掛かってきた。
札幌の息子の嫁からである。
「お父さん、
Hkが、おじいちゃんに電話しても出ないと言っています」
「お風呂に入っていたんですよ」
私は直ちにHkちゃんに電話した。
「お母さんから電話があった。
風呂に入っていたんだよ」
彼女は「今から、おじいちゃんの所に行ってもいいですか。
フィリピンのお土産があります」という。
実は、彼女はこの3月に研修旅行とかで
フィリピンに1週間ほど出掛けていた。
その折に、小遣いを渡しておいたので、お土産を買ってきたのだ。
彼女はやって来たが、お土産を渡して直ぐに帰るという。
私は、今から夕食だから、一緒に食事しようと誘った。
それで、回転寿司に出掛けた次第である。
(つまらぬ話で、恐縮である)
Satoh: Photo
Collection

「さくらんぼ」
Cactus
Cultivated by Dr.Nozaki

「テロカクタス・ラウセリー(和名なし)」
比較的最近の発見種で、メキシコ・コワウィラ州に産します。