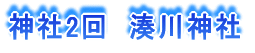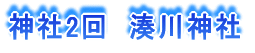
湊川神社は楠木正成を祀る神社です。
地元では親しみを込めて「楠公(なんこう)さん」と呼ばれています。
鎌倉時代の末期、
楠木正成は足利尊氏らと共に鎌倉幕府・討幕の原動力となりました。
その後、後醍醐天皇を中心とした「建武の中興」への不満を抱いた尊氏は、
天皇への反旗を翻しましたが、正成は最後まで天皇への忠誠を貫いたのでした。
湊川神社は、1872年(明治5年)、明治天皇の御沙汰により、
楠木正成の墓地、
殉節地(じゅんせつち:正義のために命を捧げた場所)などを
境内に定めて創建されました。

表門

鳥居と参道

拝殿

拝殿天井画
中央の「大青龍」は福田眉仙(ふくだびせん1875-1963)の作

楠木正成戦没地 (殉節地)

楠木正成墓碑地
表門の横に楠木正成の墓があります。
(神社にお墓というのも、おかしいと思うのですが)

徳川光圀公(水戸黄門)銅像
湊川神社に、なぜ、水戸黄門の像があるのか?
実は、楠木正成の墓を造ったのは徳川光圀であり、
その後に、明治天皇が湊川神社を創建したのです。
(この辺の成り行きについては、下の「神社めぐりメモ」の項に詳述した)

楠本稲荷神社
湊川神社の末社で、境内にあります。

菊水天満神社
湊川神社の境内には、
楠本稲荷神社と菊水天満神社の2社の境内社がおまつりされています。

宝物殿
楠木正成ゆかりの資料を所蔵、展示してあります。

楠木正成像
横山大観筆「大楠公」です。
1935年(昭和10年)、
大楠公(楠木正成)600年大祭にあたり奉納された横山大観伯の力作です。
神社めぐりメモ
「湊川神社」
歴史のおさらいをしておこう。
鎌倉時代の末期、時の執権北条高時(ほうじょう たかとき)は、
はなはだ暗愚で、政治はいっこうにかえりみず、
日夜の遊宴にふけり、闘犬に熱中して「犬公方」とあだ名されていたが、
このことは、後醍醐天皇に討幕の好機会を与えた。
しかし、天皇の計画は、裏切り者の密告で幕府に知られ、
捉えられて隠岐島に流される(1331年)。
一たび、公然と後醍醐天皇による討幕の旗が上がると、
近畿・中国の武士をはじめ、反北条氏勢力がつぎつぎに立ち上がった。
その筆頭が、
河内の金剛山のふもとを根拠とする地侍の首領、
楠木正成(1294-1336年)であった。
(千早城における北条氏率いる幕府軍と
楠木正成とのゲリラ戦は有名であるが、省略する)
1333年、後醍醐天皇は隠岐を脱出する。
天皇を支援する楠木正成、足利尊氏、新田義貞により
北条氏一族は滅ぼされ、鎌倉幕府は滅亡した。
ここに、後醍醐天皇は政権を握り、天皇政治が復活する(建武の中興)。
しかし、歴史は既に武士の時代であり、
天皇の政治は、封建制の発展という歴史の大勢に逆行するもので、
政権をにぎって一年も持たなかった。
足利尊氏が朝廷に反旗をひるがえしたのである。
楠木正成は、最後まで後醍醐天皇の側に立った。
ここに楠木正成(および新田義貞)と足利尊氏との戦いが起こり、
尊氏を九州に敗走させる。
足利尊氏は九州で大友、島津らの援助をうけ、
ふたたび大軍を率いて、京都に攻め上ってきた。
1336年7月4日、湊川において、
後醍醐天皇の命を受けた楠木正成・新田義貞の軍と、
足利尊氏・足利直義兄弟の軍との間で戦いが起こる(湊川の戦)。
時代の流れは尊氏に味方した。
天皇の政治は、不当に武士の所領を没収し、
皇族・貴族の荘園支配の復活をはかるなど武士たちを失望させた。
また、重税を課して民衆の朝廷に対する不満は、旧幕府に対するより高まった。
湊川の戦いでは、天皇に味方する武士は少なかった。
楠木正成は、この時代の流れを読んでおり、
負けると分かっていて戦いに臨んだのである。
この時のエピソードが楠木正成・正行親子の「桜井の別れ」である。
(桜井は、京都と大阪の県境にあり、過って、小生はこの近くに住んでいた)
正成は、数え11歳の正行を呼び寄せて「お前は故郷の河内へ帰す」と告げた。
「最後まで父上と共に」と懇願する正行に対し、
正成は「お前を帰すのは、自分が討死にした後のことを考えてのことだ。
天皇のために、お前は命を惜しみ、忠義の心を失わず、
いつの日か必ず朝敵を滅ぼせ」と諭したという。
「湊川の戦い」は楠木正成軍の大敗で、正成は弟の正季と刺し違えて自刃する。
以上の物語は「太平記」に詳しい。
徳川光圀(水戸黄門)は、
若い頃、司馬遷により編纂された中国の歴史書「史記」を読んで感銘をうけ、
人の心を打つのは史書であると思い、「大日本史」の編纂に着手する。
「太平記」によって英雄化された楠木正成は、
皇室に忠義を尽くした一番の忠臣と考えられ、
光圀は正成の顕彰のための建碑(けんぴ:石碑を建てる)を思いついたのである(1692年)。
(従って、正成が自刃した1336年以後、1692年まで墓石は無かったことになる)
墓碑創建に実際に動いたのは、
光圀の命をうけた「助さん」こと佐々宗淳(さっさ むねきよ)である。
佐々宗淳は、もと京都妙心寺の僧で、
還俗(げんぞく:一度出家した者が俗人にもどる)し、
水戸藩に仕えることとなった人物である。
楠木正成は、江戸時代を通じて英雄として尊敬されてきた。
明治時代になり、
皇室に忠義を尽くした人物として明治天皇の命により神社が建てられることになった。
神社の創建には、薩摩、尾張、水戸藩などが主導権を争ったが、
最終的には神社は国家が祀るものとして、
政府が主導して建てられた(1872年:明治5年)。
社名の候補としては、
「大楠霊神社」と「南木神社」と「湊川神社」案があったが、
政府は「湊川神社」案を採用した
(理由は明らかではない)。
この回のトップページ

|
湊川神社・表門
湊川神社は、楠木正成を祀る神社です。
前回の須磨寺が「平家物語」なら、湊川神社は「太平記」の舞台です。
1336年、楠木正成は「湊川の戦い」で足利尊氏に敗れ自刃します。
湊川神社が創建されたのは、
後年(1872年;明治5年)になってからで、明治天皇の命によります。
(「楠木正成」、ならびに「湊川神社創建の経緯」については
本文(神社2回 湊川神社)の「神社めぐりメモ」に詳述した)

拝殿(社殿)
太平洋戦争(神戸大空襲)で焼失したものを
1952年(昭和27年)に復興新築されました。
鉄筋コンクリート造で、
戦後の新しい神社建築様式として代表的な建物と言われています。

楠木正成・殉節地
「湊川の戦い」で楠木正成が弟の正季(まさすえ)と
刺し違えて自刃した場所です(国指定文化財史蹟)。
今回の神社: 神社2回 湊川神社
前回:寺9回 須磨寺
(次回の更新予定: 10月1日)
|
近況
(2019年9月16日
記)
八月の末に涼しくなったかと思ったら、
九月になると猛暑復活で、真夏に逆戻りである。
このホームページを更新するために、
寺参りをせねばならないが、
この猛暑では遠出する気になれない。
それで近くの神社仏閣で済ますことにしている。
前回は須磨寺、今回は湊川神社である。
いずれも私の住んでいる所から極々近い。
彼岸が過ぎて、涼しくなったら奈良方面に出掛けようと思う。
先日、その暑い時期に台風がやってきた。
関西方面は何ともなかったが、関東地方は大変だ。
とりわけ千葉県がひどかった。
今回の災害の特徴は、停電と断水である。
当初、93万戸が停電したという。
一戸あたり家族が2人強いるとすると
200万人ほどの人々が被害を受けたことになる。
これを書いている時点で(台風の4日後)、
まだ20万戸以上が停電している。
現代の文明は、電気で動いている。
電気が止まればどうにもならない。
この猛暑にクーラーは動かない。
テレビも携帯も駄目である。
電気が止まれば水も止まる。
断水になれば風呂に入れず、トイレにも行けない。
テレビのニュースを見ていて、
改めて、今の世は電気で動いているのだ、という事を痛感する。
電気がこなければ、この世は惨状を呈するのである。
ところが、その災害の復興に、
当初、政府は全く動かなかった。
すべて東京電力まかせだったのである。
台風がきたその日、安倍政権は内閣改造とかで、
災害に見向きもしなかった。
即刻、自衛隊を出動させるべきであった。
さすれば、水と電気は何とかすることが出来たはずである。
自衛隊の機動力をもってすれば、水は何とでもなる。
また、電気は「移動電源車」というものがあるのだ。
今回、つくづく思うのは、
「水と電気は、人が生きるための根幹である」ということだ。
さて、私自身のことである。
先日、内科病院に行って来た。
胃のポリープの生検の結果を聞くためである。
良性で問題ないとのことであった。
私は、止めていた酒(ビール)を飲み出した。
それを待ちかねたように、友人達との飲み会が始まった。
あちこちから声が掛かってきたのである。
有難いことではあるが、私の酒の飲み方がよくない。
「飲み会」の翌日は、必ず二日酔いである。
毎日のようにビールを飲んでいると、
凹んでいた腹が出てきた。
結果として、腹の皺が薄れてきた。
私の肉体もゲンキンなものである。
大相撲九月場所は佳境に入って来た。
相撲が始まる前は、
今場所は詰まらないだろうなぁ、と思っているのだが、
いざ始まってみると、だんだん面白くなってくる。
7日目が終わった段階で、これを書いている。
一人横綱の鶴竜が、なんと三連敗である。
これにはがっかりした。
だいたい、負け方がよろしくない。
注目の貴景勝は、
10勝を挙げれば大関復帰なのだが、現在5勝2敗である。
ここのところ連敗で、果たして10勝できるかどうか。
カド番の栃ノ心が2勝5敗で、多分大関陥落であろう。
応援している力士の一人なのだが、残念ながら陥落だ。
以前にも言ったが、
ケガで幕下の方まで落ちて大関まで上がってきたのである。
それで十分ではないか。
これから平幕で永く勤めればよろしい。
同じくカド番の豪栄道は5勝2敗で、こちらは多分大丈夫だ。
応援している力士で、小生としてもほっとしている。
同じ境川部屋の妙義龍(兵庫県出身)も元気で気分がよろしい。
遠藤が、今までとは違う強さである。
一皮むけた感じだ。
ケガがよくなったか、開眼したか。
驚いたのは、隠岐の海が全勝である。
これは出来過ぎで、その内に負けるであろう。
何といっても、一番面白いのは炎鵬である。
毎日、炎鵬の取組みを楽しみにしている。
しかし、あの小さい体で、疲れるのではあるまいか。
現在、5勝2敗だが千秋楽まで持つかどうかだ。
御嶽海が6勝1敗で元気だが、
この力士は稽古場では弱いという。
稽古も、あまりやらないらしい。
それで、体力が持たず、後半には負けだすのである。
大関候補の筆頭なのだから、頑張ってほしい。
朝乃山が1横綱2大関(鶴竜、豪栄道、栃ノ心)に勝って、
上位陣総なめである。
先に平幕で優勝したのはフロックではない。
力があるのだ。
あるいは、こちらが大関候補の筆頭かも知れない。
はてさて、優勝の行方はいかに?

先日の9月13日は「中秋の名月」であった。
夜中に起きて空を見るのだが、
あいにく雲が掛かっていて月は見えない。
しかし、満月は次の日の14日だという
(「中秋の名月」と満月とは、必ずしも一致するわけではない)。
14日の夜、10時ごろ屋上のテラスに出てみると、
それは見事な月であった(上の写真)。
いったん寝て、朝方、つまり15日の4時ごろ目が覚めて、
再度テラスに出てみた。
月は西に傾いていたが、やはり見事な月であった。
|