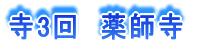薬師寺伽藍図

中門より西塔を望む

金堂
1976年に再建されています。
奈良時代・仏教彫刻の最高傑作の一つとされる本尊薬師三尊像(国宝)が
安置されています(仏像の撮影禁止で載せる事が出来ません)。

西塔
金堂を挟んで、東塔と対照的な位置に建っています。
旧塔は1528年に焼失し、現在の建物は1981年に再建されたものです。
六重塔に見えますが、三重塔です。
各層に裳階(もろこし)と言われる小さな屋根があり、
この大小の屋根の重なりがリズミカルな美しさをかもし出しています。

大講堂
2003年の再建。本尊の銅造三尊像(重要文化財)が安置されています。

回廊

桜と西塔

玄奘三蔵院・伽藍への道

玄奘三蔵院
1991年に建てられたもので、玄奘三蔵を祀ってあります。
玄奘三蔵は、例の孫悟空「西遊記」に出て来る玄奘三蔵です。
玄奘三蔵は法相宗の開祖で、薬師寺は法相宗の大本山です。
古寺巡礼・メモ
「薬師寺」
古寺巡礼を初めて、二ヶ月が過ぎた。
しかし、小生、神も仏も信じる者ではない。
お寺の人に「よう、お参りになりました」などと言われると、
何といったらよいか、肩身の狭いというか、居心地の悪い思いをする。
寺の建物も仏像も、芸術品として見ているのであって、宗教心とは関係がないのだ。
これから、この関係に、どのように折り合いを付けてゆくか、悩むところである。
さて、薬師寺である。
この寺を訪れて、先ず感じるのは、
キンキラキンの建物ばかりである、ということだ。
ほとんどの建物が、東塔以外は建て直されたものなのだ。
その国宝、東塔も、現在解体修理中である。
「大和古寺風物詩」の著者、亀井勝一郎氏は、次のように言う。
「古寺の美しさは、それが荒廃のまま、まさに崩れんとするところにある」
私もこの言辞に賛成である。
キンキラキンのお寺など、興ざめである。
従って、薬師寺の良さは、建物にあるのではない。
仏像である。
金堂の本尊、薬師如来像と脇侍の日光、月光両菩薩、
それに東院堂の本尊、聖観音立像である。
いずれも金属の金胴仏で、飛鳥時代の作である。
建物は焼けても仏は生き延びてきた。
大化の改新後、中大兄皇子は天智天皇になり、
その弟が壬申の乱の後に、天武天皇となった。
この天武天皇の時代に白鳳文化の花が開いたのであった。
天皇の発願で藤原京に建てられた薬師寺(元薬師寺という)は、後に平城京に移転する。
新しい薬師寺(平城薬師寺)の建物は新しくなったが
(移建か新造かの「薬師寺論争」があるが、最近の発掘調査で移建説は否定された)、
仏像は元薬師寺のものである。
つまり、1300年の歴史を背負っているのは、この仏様だけなのだ。
私は、薬師寺の仏像は美しいと思う。
(このホームページに仏像の写真を掲げて、見て頂きたいのだが、
残念ながら、どの寺でも仏像の撮影は禁止されている。
従って、今後も写真を掲載することはできない。
興味のある方は、土門拳の写真集を見られたい)。
これらの仏像を作った人は、どのような人物か。
鎌倉時代の仏師とは異なり、この時代の作者の名は残されていない。
しかし、天才ではないか。
かの古代ギリシャ彫刻に匹敵する名作ではないかと思う。
飛鳥時代と言えば、ようやく仏教文化が定着しようとする時期である。
そんな時代に、このような仏像が作成された。
当時の造形美術は、驚くべき高さに達していたのである。
この回のトップページ

|
薬師寺、金堂
日本最古の寺は飛鳥寺で、次いで法隆寺、
その次に位置するのが薬師寺でしょう。
飛鳥時代に建立され(藤原京:680年)、
都が平城京に移ると現在地に移転したと言われています。

西塔
薬師寺の自慢(象徴)は、二つの塔(東塔と西塔)です。
六重塔に見えますが、三重塔です。
西塔は1528年に焼失し、現在の塔は1981年に再建されたものです。
東塔は国宝で、奈良時代にさかのぼる唯一のものですが、
現在、解体修理中(2009年-2020年)で見ることができません。

大講堂
この建物も1976年に再建されたもので、
薬師寺の伽藍最大の建造物です。
今回の寺 寺3回 薬師寺
(目次トップに移動しました)
前回:城2回 大阪城
(次回の更新予定: 5月月1日)
|
近況
(2019年4月16日記)
桜の盛りも過ぎて、これからは陽気な季節である。
ところが、寒の戻りで、先日、東の方では桜に雪が降ったとか。
そろそろパッチ(股引)を脱ごうかと思っていたのだが、
今しばらく、衣替えはお預けである。
先日、山の仲間の?氏から電話が掛かってきた。
「花見のついでに拙宅に寄って欲しい」と言われる。
M氏(80歳)は、2年ほど前、膀胱に癌が見つかった。
最初の手術では膀胱の内側に出来たポリープ状の癌を除去したのだが、
その後、外側にも癌が出来て、膀胱を切除せねばならなくなった。
膀胱を除去すると、
体の外にオシッコを貯める袋をぶら下げる必要があった。
最初の手術後は至って元気であった。
2度目の手術(膀胱摘出)後も元気に、
毎日のように東山に登って来られた。
山の仲間は「無理をされないように」と気にするほどである。
飲み会にも必ず出席されていた。
膀胱代わりの袋を身に付けてである。
ところが、最近、癌が骨に転移していることが分かった。
手術は無理で薬物療法が始まった。
定期的に入院して制癌剤の投与を受けられるのだが、
この薬の副作用がきついらしい。
食欲が無く、髪の毛も抜けてきた。
メールで、その辛さを知らせてこられる。
もちろん、東山には御無沙汰である。
話を元に戻す。
M氏宅の近くに、「妙法寺川公園」の桜の名所がある。
私は、昨年、M氏に案内してもらった。
りっぱな桜の名所である(桜の名所と言って何ら異存はない)。
4月6日、午後1時に地下鉄「板宿」の改札口に、
山の仲間5人が集合した。
85歳の長老N氏、83歳の御大U氏、それに80歳のK氏、79歳のH氏、
それに77歳の小生である。
私が一番若い。
5名がお伺いすることは、事前にM氏に知らせてあって、
当日、駅まで迎えに来て下さった。
M氏と会うのは久しぶりである。
この1月の新年会以来ではあるまいか。
メールの文面から、どんな具合か心配していたのだが、元気そうである。
M氏宅で、ビールなどを頂いて、
ちょっといい気分で桜見物ということに相成った。
妙法寺川の川沿いに桜並木が続いている。
良い天気で暖かく、絶好の花見日和である。
桜はほぼ満開であった。
私は盛んにカメラのシャッターを切った。
M氏が楽しそうなのが何よりである。

帰途、山の仲間のKさんのマンションが見えたので、御大U氏は
「電話して呼び出そうか」という。
Kさんは女性で最年長、確か83歳のはずである。
ずっと東山に登ってこられていたのだが、
最近は、さすがに歳には勝てず、登って来られない。
Kさんが登って来られた時は、
急な坂道では85歳の長老N氏が、手を差し伸べてサポートされていた。
電話すると、Kさんは出てくるらしい。
それで、われわれ5人は、桜の木の下で待つことになった。
Kさんは高齢だが美しい方である。
身支度に時間のかかるのは仕方がない。
彼女が来て、再度花見ということになった。
来た道を引き返したのである。
長老N氏とKさんは、楽しそうに手をつないで歩いていた。
85歳と83歳のカップルである。